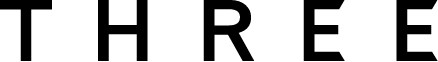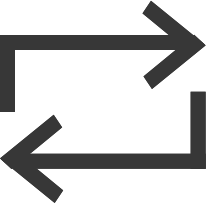「部分」としての美、「動き」としての美。

ふと思いついて、私は紙谷さんに、こんなことを聞いてみた。
「もし、非の打ちどころのないような、内面も外面も完全に美しい人がいたら、紙谷さんは、ティアラをつくりたいと思いますか?」
紙谷さんは、これに、即答した。
「作らないですね、だって、要らないですよね」。
「美しさ」は、おそらく、「部分」なのだ。私たちのほんの一部分が、美しい。
「完全に美しいもの」を想像すると、なぜかそれは蝋人形のようにとりつくしまもない、働きかけがたいイメージが浮かぶ。私たちとは一切何の関係もないような、生命を拒否するようなイメージが湧いてくる。
たとえば、私はこんなシーンを思い出した。
「白い装いをし、アンがまわりに入れた優美な花の中にうずもれて横たわったルビーの美しさは、何年ものあとまで、人々の記憶に残り、アヴォンリーの語り草とされた。ルビーはもとから美しかったが、その美は地上的であり、俗っぽかった。(中略)然し、死がそれに触れ、清め、優雅な肉づきとこれまで見られなかった清純な輪郭を残した –– 人生と愛と大きな悲哀と女の深い喜びがルビーの上に与えたかも知れぬ変貌を死が果たしたのである。」(『アンの愛情』モンゴメリ著 新潮社刊)
つまり、屍体の美である。「ロミオとジュリエット」の恋と死が完全な美しさをもって感じられるように、一点の曇も無い美しさの中には、死がある。あるいは、なにかが失われていく予感がある。生きる者を寄せ付けない遮断がある。

かつて「アイドルはトイレに行かない」というようなジョークともとれぬ話があったが、完全な美というイメージは、人の排泄とか、食欲とか、そうした当たり前の生命活動まで、ナイロンの上をすべる水滴のようにはね飛ばしてしまう。
食べるという行為はふしぎだ。口に入れるための食物は、皿の上にある時、限りなく清潔である。誰でもがそれを口にできる。しかし、たった一瞬でも誰かの口に入った瞬間、それを他の人間の口に入れ直すことは、ほとんど不可能になる。その人以外の人間にとっては、「穢れたもの」となってしまう。
この危険な行為を「美しくする」ために、幾多の「マナー」が考案された。マナーは、私たちの生理的な活動である唾液の分泌や咀嚼、口元の汚れといったできごとを、徹底的に「隠す」。生きることの生々しさを隠し、切り離したとき、私たちはそこに「美しいマナー」を感じ、安心できるわけだ。
幼い子供にはよだれかけが必要なように、放っておけば私たちは、生き物としての活動の方に、自然に流れていく。これを否定し遮断し、隠し通そうというのが、「美」なのか。
であるならば、生きている「美」は、かならず、その人のごく一部分にとどまらざるを得ない。美は、部分なのだ。
ともすれば流され、だらけていこうとする自分のなかに、必死にルールを作り、自分と戦い、内なる「美」を生きようとするとき、私たちは少しだけ美しくなる。
その「少しだけ美しい部分」を通して、他者が私たちを見る。
そこから、なにかが始まる、こともある。場合によっては、そうした「美しい部分」は見過ごされ、私たちは孤独に、自分だけの美を生きることもある。
誰にも理解されなくても、受け入れられなくても、自分は自分のいのちの流れに負けぬよう、増大するエントロピーに逆らって必死に何かを純化させ続ける。その孤独な、ごく部分的な営為が、美の活動ということなのではないだろうか。

多分、美は一つの運動なのだ。
もし、美がすべてを完全に覆い尽くしてしまったら、運動は止まる。もはや運動しなくなったものは、死んでしまう。そこで幻のように、美もいのちを失う。
段差があるから、水が流れる。私たちはその水の流れを「いきいきとして美しい」と感じる。段差がなくなると、水は流れを止める。流れなくなった水はよどみ、もはや美しいとは感じられなくなる。
紙谷さんは、人が持つ美しさがもし、見える形になれば「その人の自信になると思うんです」という。
自信とはなんだろう。
私たちは日々、なにかに飲み込まれまいとして必死に戦っている。戦いの相手は様々だ。自分を押さえつけようとするもの、否定するものとの戦い。怠惰や貪欲など、自分自身との戦い。災害や不幸、病や死と戦っている人もいるだろう。自信とは、そうした戦いに勝てないまでも負けずにいられる、という自負を言うのではないか。
であるならば、「人の持つ美しさ」がもし、可視化されたとき「自信になる」というのは、頷ける。
自分で自分の姿を、肉眼で見ることはできない。
鏡や映像のような、ゆがんだ形で見ることはできても、私たちが他人に生で接するような形では一生、自分に接することができない。
自分の内なる美しさのようなものも、多分、それと同じで、一生目にすることはできないのだろう。もしそれが「部分」であり、「動き」であるならば、なおさらだ。
紙谷さんはそれを敢えて形にして「見せる」ことがしたいのかもしれない。

人間は、巨大な望遠鏡を宇宙まで飛ばして世界の果てを見ようとしたり、決して肉眼で捉えることのできない細胞や原子を見ようとしたりする。
見えないものを見ようとする、という私たち生来の激しい衝動もまた、「美」のひとつだと言えるような気がする。
子供が大きく瞳を見開いて、一心に星や虫を追いかけている様は、美しいとしか言いようがない。